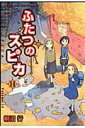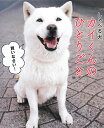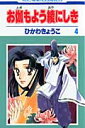Hatch!!!!!!(6)
2008年6月22日 読書
でたっ!
と言ってもお化けではなく。
猫である。
もう6冊目。
ブログの方も抜かりなく目を通しているので、「それなら本を買わなくても…」となりそうなものだが、はっちゃんに関してはなにかが違う(笑)
だって、病院にPCは持ち込めないんだよ〜大部屋だし。
はぁ〜動物って癒されるわ。
本当は犬の方が好きだけど(笑)
この際(?)猫でもいい。
猫も好きだから。
とりあえず居たら、写真を撮ろうと思うぐらい好きだから。
はっちゃんの飼い主さんは写真家さんなので、魅力最大限に発揮できる。
そういう意味ではっちゃんは幸せ者だ。
ただ、カメラアングルが良いとか、写真がきれいだとか、それだけでは誰もこんなに夢中にならないだろう。
そりゃ、やっぱり。
大阪の人ですから。
写真についてるコメントなどが最高に笑える。
うまい!
落ちがある!(当たり前だが…)
そのあたりの功績が高いと、私なぞは思うのです。
と言ってもお化けではなく。
猫である。
もう6冊目。
ブログの方も抜かりなく目を通しているので、「それなら本を買わなくても…」となりそうなものだが、はっちゃんに関してはなにかが違う(笑)
だって、病院にPCは持ち込めないんだよ〜大部屋だし。
はぁ〜動物って癒されるわ。
本当は犬の方が好きだけど(笑)
この際(?)猫でもいい。
猫も好きだから。
とりあえず居たら、写真を撮ろうと思うぐらい好きだから。
はっちゃんの飼い主さんは写真家さんなので、魅力最大限に発揮できる。
そういう意味ではっちゃんは幸せ者だ。
ただ、カメラアングルが良いとか、写真がきれいだとか、それだけでは誰もこんなに夢中にならないだろう。
そりゃ、やっぱり。
大阪の人ですから。
写真についてるコメントなどが最高に笑える。
うまい!
落ちがある!(当たり前だが…)
そのあたりの功績が高いと、私なぞは思うのです。
病院の病棟文庫に新しい漫画出現(笑)
戦国時代。
働いても働いても、田畑は荒らされ、略奪され、果ては虫けらのように殺される。
そんな百姓たちが、親や兄弟子供を殺された生き残りの百姓や樵たちがひとつにまとまった。
それが野盗である。
はじめは弱い百姓、村を襲っていた彼らも、自分たちが何故野盗になったかを思直し、やがて武士を、自分たちをこういう目にあわせた"強いものたち"を襲撃するようになる。
はじめはこわごわと。
しかし次第に大胆に。
…という話で、なかには報われぬ恋とか、裏切りとか、次第に買うを減らしてゆく野盗たちとか。
反社会集団がどこであれだれであれ、やがては辿る悲惨な結末へと流れてゆくのだ。
見舞客の分際で(笑)、漫画が多いと文句を言う○●な集団がいたが、病院に漫画が多いのは当たり前。
辛気臭い小説や面倒くさいストーリーや複雑な問題追及本なんか読んでられないもんねー。ただでさえしんどいのに。
病院では口のきき方に注意をしたほうがいいんじゃないのかな。
戦国時代。
働いても働いても、田畑は荒らされ、略奪され、果ては虫けらのように殺される。
そんな百姓たちが、親や兄弟子供を殺された生き残りの百姓や樵たちがひとつにまとまった。
それが野盗である。
はじめは弱い百姓、村を襲っていた彼らも、自分たちが何故野盗になったかを思直し、やがて武士を、自分たちをこういう目にあわせた"強いものたち"を襲撃するようになる。
はじめはこわごわと。
しかし次第に大胆に。
…という話で、なかには報われぬ恋とか、裏切りとか、次第に買うを減らしてゆく野盗たちとか。
反社会集団がどこであれだれであれ、やがては辿る悲惨な結末へと流れてゆくのだ。
見舞客の分際で(笑)、漫画が多いと文句を言う○●な集団がいたが、病院に漫画が多いのは当たり前。
辛気臭い小説や面倒くさいストーリーや複雑な問題追及本なんか読んでられないもんねー。ただでさえしんどいのに。
病院では口のきき方に注意をしたほうがいいんじゃないのかな。
病院に持ち込んだ一冊。
寸前に入手して、そのつもりで読まずに我慢しておいといたのだった。
これはちょっと昔の話。
昭和57年初出。
だから人間関係が違う。
微妙どころか、だいぶ違う(笑)
まず、十津川警部。
独身で、婚約者・妙子(もちろんのちの奥さん・直子とは別人)のことで悩んでいる。
でもって、やたら煩悩(悩み事)にとらわれている様子というか、若いというか。
私たちが現在、テレビドラマや小説で目にする十津川警部は、事件を一歩引いたところから観ている。
若手刑事が突っ走ると、まあまあちょっと待て、一歩おいて熟考してみよう、という感じなのだが、この小説では頭から事件に突入しているような感じだ。
ずいぶん違う十津川警部。
これは著者の心境の違い、書き方の違い、人物設定の違いなど、その歴史自体を感じられて面白い。
話自体も生々しくて、複雑(現在の小説は結構シンプル)で、重い。
過去の十津川警部を知らない(笑)身としては、ちょっと驚きの一冊だった。
寸前に入手して、そのつもりで読まずに我慢しておいといたのだった。
これはちょっと昔の話。
昭和57年初出。
だから人間関係が違う。
微妙どころか、だいぶ違う(笑)
まず、十津川警部。
独身で、婚約者・妙子(もちろんのちの奥さん・直子とは別人)のことで悩んでいる。
でもって、やたら煩悩(悩み事)にとらわれている様子というか、若いというか。
私たちが現在、テレビドラマや小説で目にする十津川警部は、事件を一歩引いたところから観ている。
若手刑事が突っ走ると、まあまあちょっと待て、一歩おいて熟考してみよう、という感じなのだが、この小説では頭から事件に突入しているような感じだ。
ずいぶん違う十津川警部。
これは著者の心境の違い、書き方の違い、人物設定の違いなど、その歴史自体を感じられて面白い。
話自体も生々しくて、複雑(現在の小説は結構シンプル)で、重い。
過去の十津川警部を知らない(笑)身としては、ちょっと驚きの一冊だった。
映画を見て、それで興味をもったものだ。
第二次世界大戦直後、戦犯を裁くための裁判で、法廷闘争をあきらめなかった東海郡管区司令官・岡田資(たすく)中将の裁判記録をまとめたものである。
著者は大岡昇平である。
映画の題名は「明日への遺言」である。
主演は藤田まこと。
岡田中将以下が裁かれた罪は、爆撃後のアメリカ爆撃機の搭乗員が、日本国内に不時着したのを、正式な裁判にかけずに斬首など処刑した、ということである。
これに対し、岡田中将は、責任は自分一人が負う。
ただし、まっとうな扱いは捕虜に対して行われるものであって、無差別爆撃というジュネーブ条約違反の行為を行った爆撃機の搭乗員は捕虜ではない、戦争犯罪人である。
よって、司令官の一存にて処刑されたのであると。
そこで裁判は、無差別爆撃であったかどうか、そこから話は広がって、アメリカが東京や大阪ほか各地で行った、"爆撃"そして原子爆弾に至るまで、それは違法なのではないか、という大きな問いかけあるいは法廷闘争をに話は発展したのである。
岡田中将は処刑(死刑)を覚悟したうえで、アメリカ軍の無差別攻撃を明らかにせんとした…
以下は、映画鑑賞後の私の感想から。(手抜き〜)(笑)
パール博士で思い出した!
ボースも本を買っていたんだった!!
第二次世界大戦直後、戦犯を裁くための裁判で、法廷闘争をあきらめなかった東海郡管区司令官・岡田資(たすく)中将の裁判記録をまとめたものである。
著者は大岡昇平である。
映画の題名は「明日への遺言」である。
主演は藤田まこと。
岡田中将以下が裁かれた罪は、爆撃後のアメリカ爆撃機の搭乗員が、日本国内に不時着したのを、正式な裁判にかけずに斬首など処刑した、ということである。
これに対し、岡田中将は、責任は自分一人が負う。
ただし、まっとうな扱いは捕虜に対して行われるものであって、無差別爆撃というジュネーブ条約違反の行為を行った爆撃機の搭乗員は捕虜ではない、戦争犯罪人である。
よって、司令官の一存にて処刑されたのであると。
そこで裁判は、無差別爆撃であったかどうか、そこから話は広がって、アメリカが東京や大阪ほか各地で行った、"爆撃"そして原子爆弾に至るまで、それは違法なのではないか、という大きな問いかけあるいは法廷闘争をに話は発展したのである。
岡田中将は処刑(死刑)を覚悟したうえで、アメリカ軍の無差別攻撃を明らかにせんとした…
以下は、映画鑑賞後の私の感想から。(手抜き〜)(笑)
これは敗戦間近の日本、東海方面司令であった、岡田資(たすく)中将を裁いた軍事裁判の物語である。
同時期に東京巣鴨プリズンに収監された東条英機らの裁判、極東軍事裁判もあった。
こちらはとっても有名なんだけど、敗戦国日本の軍人達は、色んな場所で、いろんな国(勝利国)によって裁かれ、最終的には千名以上が亡くなった。
病死・自決を入れてのことではあるが、それらを省いても優に千名近くの人数である。
岡田中将が問われている罪は、名古屋を無差別爆撃した爆撃機の搭乗員を処刑したこと。
捕虜として十分な裁判を受けさせなかったこと。
アメリカ軍が行なう裁判は裁判官・検事のみならず、弁護士もアメリカ人である。
そのことへの不安感は無いといえばウソになる。
岡田中将の家族も、同じことを思っていたようだが…
戦争の復讐。
それをやろうとするのではないか?
そう思っても仕方が無い。
東京裁判を見ればその片鱗を感じずにはいられない。
今の私たちでも。
だが、アメリカ人弁護士は言う。
私はフェアにやりたいだけだ、と。
こういうところ。
流石だな、と思うところだ。
今時の日本人はすぐに阿る。
それが浅ましい。
岡田中将は言う。
無差別爆撃こそがジュネーブ条約違反であると。
軍需工場の無い場所、非戦闘民を対象に行なわれた、焼夷弾と機銃照射、それが無差別攻撃でないはずが無い。
パラシュートで不時着したアメリカ軍人は、捕虜ではない、戦争犯罪者である。
検事は言う。
裁判を省略して処刑するのが違法であると。
非戦闘民への無差別攻撃を責めて、アメリカ軍すべてを捌こうというのか?
裁判の主点は、アメリカ軍の非戦闘民への無差別攻撃をどう捕えるか、その有無を問う、というところにある。
岡田中将は言う。
アメリカにはアメリカの事情というものがある。
だから、裁判の結果はどうあれ、自分は自分の正義を貫く、この法争に勝つだけだ、と。
そして部下は、すべて私の命令によって動いたのである。
正義、というのは難しい言葉だ。
自分にとっての正義は他人にとっての正義ではない。
それをどう捕えるか。
どう主張するのか。
どこまで受け入れることができるのだろうか。
ただ、判決のあと、中将は法廷に、そこにいる人すべてに感謝する。心から。
無差別攻撃については、東京裁判でも他の裁判でも俎上に載せることすらできなかった。
それを思えば、この裁判ではその点について正面から論争できたことが幸いであると。
彼を誇りに思い、彼を慕い、そして彼を忘れずに生きてゆく残された人々。
日本人は、過去の戦争を忌み嫌うだけではなく、また賞賛するのではなく、そこにあるものを、そこで生きた人々が残したものをきちんと受け取らねばならないのではないだろうか。
正々堂々と正面から、当時の"焼け出された"人々の視点にたっていた日本人の思いを、そしてその思いを主張した人がいたことを。
法廷の雰囲気は、裁判官も検事も、やがて岡田中将の林とした態度に影響されてゆく。
少なからぬ尊敬の思いを抱くようになったのだと思う。
彼らや看守の呼び方自体が、「オカダ」⇒「ミスター・オカダ」⇒「閣下」と変化してゆくのがその心情を表わしているように思えた。
<以下、産経新聞の特集記事より抜粋。>
第二次世界大戦後、連合国による日本の戦争犯罪者を裁く軍事裁判が始った。東條英機元首相らA級戦犯の東京裁判での公判記録は歴史文書や記録映像などで語り伝えられているが、BC級戦犯の裁判が行なわれた横浜地方裁判所での記録を知る人は多くない。
映画「明日への遺言」の主人公、第13方面軍司令官件東海軍司令官の岡田資中将は、この戦犯裁判で戦勝国・米国に対し、たった一人で法廷闘争に挑んだ。
敗戦で自信と誇りを失ってしまった戦犯が少なくない中、岡田中将は強靭な意志と誇りで、この裁判を法による戦い=法戦と称して臨み、戦勝国の論理で裁こうとする米国の裁判官や検事と真正面から対峙、非人道的な無差別攻撃の罪を認めさせようとした。
岡田中将が選んだ選択は強固な信念に貫かれていた。昭和20年、名古屋空襲で飛来、被弾して降下してきた米軍爆撃機B29の搭乗員38人を処刑した責任を問われ、B級戦犯として横浜の軍事法廷で章23年5月、絞首刑判決を下される。が、法廷を退場する際、彼は妻に向かって一言こう告げる。「本望である」。
そして翌年9月、刑は執行され、岡田中将は59年の人生を終えた。
処刑台に向かう最期の日、彼は部下にこう言い残した。「君達は来なさんなよ」
部下に処刑の責任を負わせたり、事実を隠蔽し責任逃れに奔走したりする戦犯が少なくなかったが、岡田中将は一貫して「すべての責任は私にある」と主張。裁判に掛けられた19人の部下の罪を一人で背負う覚悟を固めていた。さらに米軍が国際法を違反し、無差別爆撃を行なった事実を後半の中で立証し、その罪を法廷で訴え続けた。
「敗戦直後の世相を見るに言語道断、何も彼も悪いことは皆、敗戦国が負うのか?なぜ堂々と世界環境の内に国家の正義を説き、国際情勢、民衆の要求、さては戦勝国の圧迫も、また重大なる戦因なりし事も明らかにしようとしないのか…」19人の部下を全員釈放させ、ただ一人死刑に処せられた岡田中将の揺るぎなき信念は現在も不変であるーと「明日への遺言」は訴える。 (以上)
パール博士の本を読んでまもなくだったので、いろいろと思いをめぐらせた。
人は自分の正義を持つ。
でも同時に他の部分に悪を作る。
お互いに認めあうこと、受け入れること。
それができない、できなくなった、その結果がこの21世紀ではないだろうか。
死刑判決を、本望と断じた中将の心境にはいまだ遠い私ではあるが、悔いの無いように、自分に正直に日々を生きて行かねばなぁと改めて思う、そういう映画だった。
今日のお客さんは、それなりに年齢の上の方が多かったけど…特に中年以上のご夫婦が多かったな。
でも、私の隣には10代の女の子が一人で見に来ていた。
ちょっと吃驚したけど…まあ別におかしなことではないかもしれない。
文化庁推薦だから見なさい、とは決して言わないが、私はしっかり生きているのかなぁ、と考えながら見ていた。
パール博士で思い出した!
ボースも本を買っていたんだった!!
普通であることの大切さ。
それを知らしめんがために著者はこの物語を書いた…って言っていいのかな?
触手な妹。
リスな妹。
そしてふつーの妹。
数々の試練を経て、曽根崎姉妹は普通世界に戻った。
一緒に旅をした"シュリン"もその武器(?)"レンチ"も"元の姿"に戻った……って、戻るのが最後になったのは、原因が●▽だったからだ。
まあ善哉善哉。
結果オーライで、アスモデウス・ミヤもベルゼブブ・ミヤも封印できたしめでたしめでたし♪
大団円♪(か?)
この語感が…(笑)
よくいろいろ突っ込めるよなぁ、この著者。
感心する。
良い意味で。
面白かったです。
それを知らしめんがために著者はこの物語を書いた…って言っていいのかな?
触手な妹。
リスな妹。
そしてふつーの妹。
数々の試練を経て、曽根崎姉妹は普通世界に戻った。
一緒に旅をした"シュリン"もその武器(?)"レンチ"も"元の姿"に戻った……って、戻るのが最後になったのは、原因が●▽だったからだ。
まあ善哉善哉。
結果オーライで、アスモデウス・ミヤもベルゼブブ・ミヤも封印できたしめでたしめでたし♪
大団円♪(か?)
この語感が…(笑)
よくいろいろ突っ込めるよなぁ、この著者。
感心する。
良い意味で。
面白かったです。
天切り松闇がたり(第1巻)
2008年5月28日 読書
ほうほう、でましたか。これ。
友人からのレンタル本なので、風評とか評判とか聞かずに読み始めた新鮮な一冊。
著者は「鉄道員(ぽっぽや)」「地下鉄(メトロ)にのって」などの作者である。
情がものをいう物語であろうと想像しつつ本を開いた。
天切り松、というのは人のあだ名。
松蔵というのが本名で、盗人である(泥棒といってはいけないらしい)
天井の、瓦を数枚どけて、屋根を破って土蔵(土蔵出なくてもいいけど)破りをし、お宝をいただいて、屋根と瓦をもとどおりにして逃げる。
見た目、盗人が侵入したかどうかすらわからない。
腕のいい大工が見ればわかる、というやり方をするのが"天切り"というらしい。
その彼も、もうとうに70歳を超えた老人で、盗人稼業からも足を洗っていた。
その彼は、警察署長の要請によって防犯の指導をするかわりに、懐かしの我が家、ならぬ未決囚監獄へお泊りすること〜を楽しみにしているのだった。
だから、一応形として手錠も腰ひももするけど、署長クラスの呼び出されて防犯指導をして、その見返りに銀座に繰り出していっぱい〜その後、牢屋へお泊りする、というわけのわからん話になっている。
わけがわからんのはそこに収監されている犯罪者たちで、最初はねぐら+食事目当てのじーさんだと馬鹿にしていたが、話をするうちに聞くうちにとんでもない大物だと気づかされる。
題名の"闇がたり"、というのは彼ら古風な盗人の特技のひとつで、6尺四方にしか声が聞こえないように語ること。
その技を持って、(周辺の房の住人に迷惑だからと)自分の過去をそしてなによりも昔の盗人がどれだけ義侠心があってどれだけ見事な腕をもっていたかを語る。
その話の内容がこの本の内容である。
…というわけで、その昔(大正時代)に東京にその名を響かせた「目細の安吉」一家。
その末席に連なっていた天切り松による、義理と人情の盗人話が花開く。
牢獄で。
歓衆は、同房のむくつけき犯罪者たちと、当直の看守と非直の看守や刑事たち…。
満員御礼だ。
料金をとった方がいいんじゃないのかな?
公爵・山形有朋元帥の話などはスケールがでかくて最高に面白かった〜
嫌われていたとは知らなかったが…そしてあの大隈重信が民衆に絶大になる人気を誇っていたとは…歴史って不思議だね。
何十年単位で意識なんて変化するものだ。
だから、ず〜っと同じ意識を国民にもたせるためには、いかに普段の不断の努力が必要かってことだな。
そう思うと、よくやるねぇ、中国は。
友人からのレンタル本なので、風評とか評判とか聞かずに読み始めた新鮮な一冊。
著者は「鉄道員(ぽっぽや)」「地下鉄(メトロ)にのって」などの作者である。
情がものをいう物語であろうと想像しつつ本を開いた。
天切り松、というのは人のあだ名。
松蔵というのが本名で、盗人である(泥棒といってはいけないらしい)
天井の、瓦を数枚どけて、屋根を破って土蔵(土蔵出なくてもいいけど)破りをし、お宝をいただいて、屋根と瓦をもとどおりにして逃げる。
見た目、盗人が侵入したかどうかすらわからない。
腕のいい大工が見ればわかる、というやり方をするのが"天切り"というらしい。
その彼も、もうとうに70歳を超えた老人で、盗人稼業からも足を洗っていた。
その彼は、警察署長の要請によって防犯の指導をするかわりに、懐かしの我が家、ならぬ未決囚監獄へお泊りすること〜を楽しみにしているのだった。
だから、一応形として手錠も腰ひももするけど、署長クラスの呼び出されて防犯指導をして、その見返りに銀座に繰り出していっぱい〜その後、牢屋へお泊りする、というわけのわからん話になっている。
わけがわからんのはそこに収監されている犯罪者たちで、最初はねぐら+食事目当てのじーさんだと馬鹿にしていたが、話をするうちに聞くうちにとんでもない大物だと気づかされる。
題名の"闇がたり"、というのは彼ら古風な盗人の特技のひとつで、6尺四方にしか声が聞こえないように語ること。
その技を持って、(周辺の房の住人に迷惑だからと)自分の過去をそしてなによりも昔の盗人がどれだけ義侠心があってどれだけ見事な腕をもっていたかを語る。
その話の内容がこの本の内容である。
…というわけで、その昔(大正時代)に東京にその名を響かせた「目細の安吉」一家。
その末席に連なっていた天切り松による、義理と人情の盗人話が花開く。
牢獄で。
歓衆は、同房のむくつけき犯罪者たちと、当直の看守と非直の看守や刑事たち…。
満員御礼だ。
料金をとった方がいいんじゃないのかな?
公爵・山形有朋元帥の話などはスケールがでかくて最高に面白かった〜
嫌われていたとは知らなかったが…そしてあの大隈重信が民衆に絶大になる人気を誇っていたとは…歴史って不思議だね。
何十年単位で意識なんて変化するものだ。
だから、ず〜っと同じ意識を国民にもたせるためには、いかに普段の不断の努力が必要かってことだな。
そう思うと、よくやるねぇ、中国は。
ふたつのスピカ(14)
2008年5月25日 読書
東京宇宙学校、地獄の特訓…を久々に見た一冊。
山越えて〜走って〜時間内にゴールだって。
鬼のような…
宇宙飛行士ってこれだけの体力と精神力がないと勤まらないとすれば、今現在宇宙を目指している人、宇宙から還って来た人を尊敬の目で見てしまう。
まぁ普通の体力じゃあまずだめだろうな。
ここまででないにしても。
失敗すればそこには死が待っている。
いつでも高確率で死ぬ可能性だけはある。
その状態を耐えてゆくわけだからさ。
どうするのかな〜前途多難みたいだけど。
それぞれの事情ってやつもはっきりしてきたしね。
でも人間、事情のない人間なんているわけない。
そういうものすべて抱えて、せっせと歩いているわけだし。
平地だろうが坂道だろうが。
他人には下り坂に見えてもね、本人には上り坂だったりする。
そういうものが見えない、というのも情けない。
山越えて〜走って〜時間内にゴールだって。
鬼のような…
宇宙飛行士ってこれだけの体力と精神力がないと勤まらないとすれば、今現在宇宙を目指している人、宇宙から還って来た人を尊敬の目で見てしまう。
まぁ普通の体力じゃあまずだめだろうな。
ここまででないにしても。
失敗すればそこには死が待っている。
いつでも高確率で死ぬ可能性だけはある。
その状態を耐えてゆくわけだからさ。
どうするのかな〜前途多難みたいだけど。
それぞれの事情ってやつもはっきりしてきたしね。
でも人間、事情のない人間なんているわけない。
そういうものすべて抱えて、せっせと歩いているわけだし。
平地だろうが坂道だろうが。
他人には下り坂に見えてもね、本人には上り坂だったりする。
そういうものが見えない、というのも情けない。
(コミック)獣神演武(02)/荒川弘
2008年5月25日 読書
妹が手に入れそこなっているので、とっとと友人からレンタル〜♪
話が動く。
オニババ(?)師匠に、岱燈の出生の秘密、皇帝の登場に王宮の陰謀らしきもの。
動く動く。
5つ星のうち3つまでが揃って、これからも期待できそう。
テンポの良さがいいね。
惜しむらくは紅英師匠の早世(いやなんか、実際にはものすご〜長生きしている雰囲気はありますが)である。
いい性格してたのにな。
それにしても、この物語では、かよわい女が出てきそうにない…
話が動く。
オニババ(?)師匠に、岱燈の出生の秘密、皇帝の登場に王宮の陰謀らしきもの。
動く動く。
5つ星のうち3つまでが揃って、これからも期待できそう。
テンポの良さがいいね。
惜しむらくは紅英師匠の早世(いやなんか、実際にはものすご〜長生きしている雰囲気はありますが)である。
いい性格してたのにな。
それにしても、この物語では、かよわい女が出てきそうにない…
母親に頼まれて注文したが、「在庫なし」で帰ってきた。
で、めげずにタイミングをずらしてもう一度注文したら今度はすんなり通った。
どうせまた、「テレビで宣伝したんやろ?」と尋ねたら、「みのさんのテレビでやった」という返事。
そんな事だろうと思った。
…食品をスーパーの棚から一掃するだけにとどまらず、本までベストセラーにしかねない勢い。
すごい影響力やね。
これは、使う言葉も慎重でないと。
母に渡す前に黙って読んでやろ(笑)
男はサケ。
帰る場所がないと外に出てゆけない。
回帰本能が強い。
そして甘えた。
弱い。
女はマス。
とっとと広大な海に出てゆく。
後ろは振り返らない。
切るときは全部切る。
(だから別れるといったら全部切り捨ててかえっちゃうから要注意)
強い。
で、めげずにタイミングをずらしてもう一度注文したら今度はすんなり通った。
どうせまた、「テレビで宣伝したんやろ?」と尋ねたら、「みのさんのテレビでやった」という返事。
そんな事だろうと思った。
…食品をスーパーの棚から一掃するだけにとどまらず、本までベストセラーにしかねない勢い。
すごい影響力やね。
これは、使う言葉も慎重でないと。
母に渡す前に黙って読んでやろ(笑)
男はサケ。
帰る場所がないと外に出てゆけない。
回帰本能が強い。
そして甘えた。
弱い。
女はマス。
とっとと広大な海に出てゆく。
後ろは振り返らない。
切るときは全部切る。
(だから別れるといったら全部切り捨ててかえっちゃうから要注意)
強い。
65歳の悠々自適の男性二人。
39歳の人妻。
25歳の孤独な女。
この四人による三角関係が読んだ殺人事件。
神話の里と言ったって、日本国中そうじゃないのという声は当然あがる。
同時に、桜を追いかけて日本を旅する…そのふたつの条件が交わるところが殺人現場だとは、なんとも浪漫チック。
不謹慎だが。
飛鳥の石舞台など、観たい史跡はいっぱいあるが、いかんせん。
隣の京都からでもなかなか交通の便が…時間がかかるというか、乗り換えが大変というか、近鉄電車は特急料金が別だから使いたくないとか、そういう複雑な事情があるので行きづらいのだ。
泊まりがけでいくか〜となるのが奈良。(その昔、室生寺にも泊まりがけで行ったものだ、朝一番でお寺に入るために)
大阪や神戸なら少々無理しても日帰りで帰ってくるというのにね。
古代史ロマンはいかにも遠い。
そういえば、お寺関係に顰蹙をかった奈良の例のマスコット。
仏様に鹿の角が生えているとしか思えないやつですが、あれって名前だけ募集して、デザインは行政が決めたらしいね。
そして仏教界からクレームが…つくのは仕方がないかなぁと私ですら思うようなデザインだな、確かに。
で、それとは別にマスコットを、今度は市民が投票で選びましょう、という候補作が何点かあがって実際に今、投票をしているらしい。
丸々太ったゴムのような鹿(その心は、すべて丸く収まるように)のデザインなどもあり、ほかのデザインもなかなかかわいらしかった。
最初のやつにケチがついた以上は、穏便にすますために、こっちの方を(公式マスコットにならないとしても)利用する人や商店が増えるのでは?と思う。
39歳の人妻。
25歳の孤独な女。
この四人による三角関係が読んだ殺人事件。
神話の里と言ったって、日本国中そうじゃないのという声は当然あがる。
同時に、桜を追いかけて日本を旅する…そのふたつの条件が交わるところが殺人現場だとは、なんとも浪漫チック。
不謹慎だが。
飛鳥の石舞台など、観たい史跡はいっぱいあるが、いかんせん。
隣の京都からでもなかなか交通の便が…時間がかかるというか、乗り換えが大変というか、近鉄電車は特急料金が別だから使いたくないとか、そういう複雑な事情があるので行きづらいのだ。
泊まりがけでいくか〜となるのが奈良。(その昔、室生寺にも泊まりがけで行ったものだ、朝一番でお寺に入るために)
大阪や神戸なら少々無理しても日帰りで帰ってくるというのにね。
古代史ロマンはいかにも遠い。
そういえば、お寺関係に顰蹙をかった奈良の例のマスコット。
仏様に鹿の角が生えているとしか思えないやつですが、あれって名前だけ募集して、デザインは行政が決めたらしいね。
そして仏教界からクレームが…つくのは仕方がないかなぁと私ですら思うようなデザインだな、確かに。
で、それとは別にマスコットを、今度は市民が投票で選びましょう、という候補作が何点かあがって実際に今、投票をしているらしい。
丸々太ったゴムのような鹿(その心は、すべて丸く収まるように)のデザインなどもあり、ほかのデザインもなかなかかわいらしかった。
最初のやつにケチがついた以上は、穏便にすますために、こっちの方を(公式マスコットにならないとしても)利用する人や商店が増えるのでは?と思う。
十津川警部「オキナワ」
2008年5月19日 読書
オキナワ、と書くのは戦争の後、アメリカと基地と政府の間でどんどん変質していった、悪いアメリカの影を落とした島のこと。
沖縄とかくのは、はるか昔からの文化を抱き、歌と踊りと太陽と海が好きな(そして目が大きくかわいらしい人が多い、たとえおじさんでも)明るい人々が棲む島のこと。
そういう意識で使い分けたという。
ゆいレールというモノレールのことは、以前に読んだ推理漫画で知っていたが、ここではもう少し詳しくかいせつしてある。
2003年8月開通。
東京モノレールとおなじ跨座式。
自動運転だけどちゃんと運転手がいる。
首里城に近づく、と思いきや直前で大きく曲がって遠のいている。
延長戦を引くための措置ではあろうが、なんか、残念…と。
沖縄に行ったことがない。
太陽と海。
車がないと不便だとは言うが、ゆいレールもあるんだし、バスもあるんだし、うろうろしたいわけじゃなし、ぜひ行ってみたいと思う。
小説の内容は、ダークな沖縄が生んだ犯罪が、沖縄出身の姉妹を苦しめる。
ここでもまた沖縄は、アメリカと本土の食い物になっている感じがする。
沖縄とかくのは、はるか昔からの文化を抱き、歌と踊りと太陽と海が好きな(そして目が大きくかわいらしい人が多い、たとえおじさんでも)明るい人々が棲む島のこと。
そういう意識で使い分けたという。
ゆいレールというモノレールのことは、以前に読んだ推理漫画で知っていたが、ここではもう少し詳しくかいせつしてある。
2003年8月開通。
東京モノレールとおなじ跨座式。
自動運転だけどちゃんと運転手がいる。
首里城に近づく、と思いきや直前で大きく曲がって遠のいている。
延長戦を引くための措置ではあろうが、なんか、残念…と。
沖縄に行ったことがない。
太陽と海。
車がないと不便だとは言うが、ゆいレールもあるんだし、バスもあるんだし、うろうろしたいわけじゃなし、ぜひ行ってみたいと思う。
小説の内容は、ダークな沖縄が生んだ犯罪が、沖縄出身の姉妹を苦しめる。
ここでもまた沖縄は、アメリカと本土の食い物になっている感じがする。
しゃべる犬カイくんのひとりごと
2008年5月16日 読書
白戸家のおとうさん。
「犬になるとは思わなかったなぁ」
「俺だって思わなかったよ」
と大きな秘密を持っている白い犬。
その正体は北海道犬のカイくんだった。
そう。
こいつは白い犬の写真集である。
別にCMの写真とカか裏話とかあるわけではないが、でも犬好きとしては押さえておきたい一冊ではないか。
ギャルのミニスカートに「ニヤリ」
おやじギャグを飛ばして満足。
実際あの表情は面白い。
考えている(反省している)猿にも迫る(と思う)
テーブルなどに足をのっけている姿も様になる。
芸達者な犬だよね。
「犬になるとは思わなかったなぁ」
「俺だって思わなかったよ」
と大きな秘密を持っている白い犬。
その正体は北海道犬のカイくんだった。
そう。
こいつは白い犬の写真集である。
別にCMの写真とカか裏話とかあるわけではないが、でも犬好きとしては押さえておきたい一冊ではないか。
ギャルのミニスカートに「ニヤリ」
おやじギャグを飛ばして満足。
実際あの表情は面白い。
考えている(反省している)猿にも迫る(と思う)
テーブルなどに足をのっけている姿も様になる。
芸達者な犬だよね。
例によって画像が〜〜!
見た目楽しくないんだよね、これだと。
西村京太郎の短編集。
そのなかの一つは既読なので、ちょっと損した気分である。
冤罪事件が多いのは、いまどきの社会現象を反映しているのだろう。
十津川警部が年をとったせいか、部下の若手刑事の活躍が目立つ。
警部だってまだ40代のはずだが…がんばれ!と思わず応援してしまう私であった。
お、今頃(5/17)出て来たわ。
画像。
見た目楽しくないんだよね、これだと。
西村京太郎の短編集。
そのなかの一つは既読なので、ちょっと損した気分である。
冤罪事件が多いのは、いまどきの社会現象を反映しているのだろう。
十津川警部が年をとったせいか、部下の若手刑事の活躍が目立つ。
警部だってまだ40代のはずだが…がんばれ!と思わず応援してしまう私であった。
お、今頃(5/17)出て来たわ。
画像。
TVアニメーション鋼の錬金術師キャラコレ
2008年5月13日 読書
レビュー、出ているのか出ていないのか。どっちでも取れる出方だし。
妹がかくして(笑)いたのを借りる。
くいうアニメーションの紹介本というか、切り取り本を見るのは久々だなぁと感慨深く眺める。
結構ぎっしり詰まっているので読む(見る)のに時間がかかる。
アニメと原作と、話が、設定が違ったのか…と今頃気づく。
死んでる人が生きていたり。
生きてる人が死んでいたり。
犯人が変わっていたり(推理ものでよく使う手だ)
人気あるよね。
参考 ⇒
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4757513178/sr=1-1/qid=1210680734/ref=dp_image_0?ie=UTF8&;
妹がかくして(笑)いたのを借りる。
くいうアニメーションの紹介本というか、切り取り本を見るのは久々だなぁと感慨深く眺める。
結構ぎっしり詰まっているので読む(見る)のに時間がかかる。
アニメと原作と、話が、設定が違ったのか…と今頃気づく。
死んでる人が生きていたり。
生きてる人が死んでいたり。
犯人が変わっていたり(推理ものでよく使う手だ)
人気あるよね。
参考 ⇒
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4757513178/sr=1-1/qid=1210680734/ref=dp_image_0?ie=UTF8&;
星野仙一「世界一」への方程式
2008年5月6日 読書
決してほめるばかりではありません…
人間には誰でも、長所と短所というものがあるわけで。
その長所が必ずしも万民にとって良いところ、というわけではないわけで。
星野仙一・北京オリンピック日本代表監督の生きざまを冷静に観察しゆえに今彼がある。
その姿を描こうとする。
最初のアジア予選の裏幕は、そんなに詳細に描かれているわけではないけれど、ああなるほどそんなことが、と思う。
彼が阪神の監督を引き受けたとき、どのような戦略をめぐらしたか。
単に人気がある、という人物ではない。
その人気の後押しを、あるいはその人気をどうやって作り上げたか。
ただのほほんと野球をやっていたわけではない。
そんな単純な人間は存在しない。
そうなんだよなぁ、と。
大変なんだよなぁ、と。
そして、
凄いんだよなぁ、と。
思うわけです。
やっぱり。
人間には誰でも、長所と短所というものがあるわけで。
その長所が必ずしも万民にとって良いところ、というわけではないわけで。
星野仙一・北京オリンピック日本代表監督の生きざまを冷静に観察しゆえに今彼がある。
その姿を描こうとする。
最初のアジア予選の裏幕は、そんなに詳細に描かれているわけではないけれど、ああなるほどそんなことが、と思う。
彼が阪神の監督を引き受けたとき、どのような戦略をめぐらしたか。
単に人気がある、という人物ではない。
その人気の後押しを、あるいはその人気をどうやって作り上げたか。
ただのほほんと野球をやっていたわけではない。
そんな単純な人間は存在しない。
そうなんだよなぁ、と。
大変なんだよなぁ、と。
そして、
凄いんだよなぁ、と。
思うわけです。
やっぱり。
お伽もよう綾にしき(第4巻)
2008年5月4日 読書
早くはないが格別遅れもせずにきちんきちんと出てくるこのシリーズ。
作者の性格だろうな。
不思議なほど、昔から変わらない絵。
室町時代の陰陽師?
不思議な力を持つ人々が、争う。
守るもの、そして侵すもの。
悪夢の正体が判明するとともに、かつての敵が●▽となって登場する。(性格は変わらず)
でもって、年齢差、という最大の難関をクリアして、彼と彼女は男女の意識をし始める。
そう、これこそが元祖・少女漫画であろう(笑)
まさしく王道である。
おじゃるさまは狐っぽいと…いう噂だったけれど、殺生石になった誰かさんよりずっとましでよかったんじゃないかな。(あれは女だが)
作者の性格だろうな。
不思議なほど、昔から変わらない絵。
室町時代の陰陽師?
不思議な力を持つ人々が、争う。
守るもの、そして侵すもの。
悪夢の正体が判明するとともに、かつての敵が●▽となって登場する。(性格は変わらず)
でもって、年齢差、という最大の難関をクリアして、彼と彼女は男女の意識をし始める。
そう、これこそが元祖・少女漫画であろう(笑)
まさしく王道である。
おじゃるさまは狐っぽいと…いう噂だったけれど、殺生石になった誰かさんよりずっとましでよかったんじゃないかな。(あれは女だが)
幻冬舎コミックス 刊
妹が、「なんか売れているらしい」と入院の無聊を慰めに持ってきてくれた一冊だ。
国を擬人化している。
たとえば、表紙を見よ。
左から、「ドイツ氏」であり「イタリア氏」であり「日本氏」である。
そのイタリアが主人公(?)で、ど〜しよ〜もないその国民性(おもに第一次・第二次大戦時の)から「ヘタリア!」と呼ばれる…らしい。
ニューヨークで美術の勉強をしている日本人男性がネットにのっけた漫画が大ヒットしたのでコミックスになったらしいが、多いなぁ、そういうの。
出版社って本気で漫画家とか作家を育てないのな。
その辺ににぎやかに派手やかに咲いているのを摘んできて、お茶を濁して、飽きられて枯れたらポイッ!という感じがして仕方がないが私の誤解だろうか?
この漫画、その発想はとても面白い。
歴史の全般(雑学含む)についてよく知っていないとこれは書けない。
それはすごい!
と、本当に思う。
思うが。
出版するなら描き直してほしかった。
同じようにWEBで爆発し出版された「となりのネネコさん」のように、直視に耐えがたい、と出版を遅らせても書き直す心意気が欲しかった。
本人はそんなつもりで描いたんじゃないかもしれない。
でも商品として値段がつくんだから。
それに、なによりも、このネタ!
この雑な(正直でごめん)絵では、勿体ないよ!!
時々かきたしたんだろうなぁ〜と思える絵はとても綺麗なんだから、なおさらだ。
(こういうところにも、出版社側の姿勢を疑うのである)
それぞれ国の擬人化なので、古い歴史のある国は、つまりそういう登場人物は、とんでもない年月を生きている。
英仏の仲の悪さは予想通りだが、けんかの最中に「また100年、暴れてやる!」などというセリフが何気に投げ捨てられるのが笑いを呼ぶ。(1338〜1453の百年戦争のこと)
ちなみにこの台詞を吐いたのは英国。
逆に細かい歴史+雑学を知っていた方が笑える。
絶対笑える。
この方面への作者の知識は本当にすごい。
つまり、なんにも知らないと笑えない要素が多いので、面白い派とそうでない派は真っ二つかもしれない。(マンガの枠外に説明文があるが…マンガを読んでから説明されてもなぁ)
PS,
後日、妹が「いらん」と言って呉れた。
う〜ん。かもね〜とは思ったが。
そして二巻は買わないと言っている。
う〜ん。どうしよう〜。
妹が、「なんか売れているらしい」と入院の無聊を慰めに持ってきてくれた一冊だ。
国を擬人化している。
たとえば、表紙を見よ。
左から、「ドイツ氏」であり「イタリア氏」であり「日本氏」である。
そのイタリアが主人公(?)で、ど〜しよ〜もないその国民性(おもに第一次・第二次大戦時の)から「ヘタリア!」と呼ばれる…らしい。
ニューヨークで美術の勉強をしている日本人男性がネットにのっけた漫画が大ヒットしたのでコミックスになったらしいが、多いなぁ、そういうの。
出版社って本気で漫画家とか作家を育てないのな。
その辺ににぎやかに派手やかに咲いているのを摘んできて、お茶を濁して、飽きられて枯れたらポイッ!という感じがして仕方がないが私の誤解だろうか?
この漫画、その発想はとても面白い。
歴史の全般(雑学含む)についてよく知っていないとこれは書けない。
それはすごい!
と、本当に思う。
思うが。
出版するなら描き直してほしかった。
同じようにWEBで爆発し出版された「となりのネネコさん」のように、直視に耐えがたい、と出版を遅らせても書き直す心意気が欲しかった。
本人はそんなつもりで描いたんじゃないかもしれない。
でも商品として値段がつくんだから。
それに、なによりも、このネタ!
この雑な(正直でごめん)絵では、勿体ないよ!!
時々かきたしたんだろうなぁ〜と思える絵はとても綺麗なんだから、なおさらだ。
(こういうところにも、出版社側の姿勢を疑うのである)
それぞれ国の擬人化なので、古い歴史のある国は、つまりそういう登場人物は、とんでもない年月を生きている。
英仏の仲の悪さは予想通りだが、けんかの最中に「また100年、暴れてやる!」などというセリフが何気に投げ捨てられるのが笑いを呼ぶ。(1338〜1453の百年戦争のこと)
ちなみにこの台詞を吐いたのは英国。
逆に細かい歴史+雑学を知っていた方が笑える。
絶対笑える。
この方面への作者の知識は本当にすごい。
つまり、なんにも知らないと笑えない要素が多いので、面白い派とそうでない派は真っ二つかもしれない。(マンガの枠外に説明文があるが…マンガを読んでから説明されてもなぁ)
PS,
後日、妹が「いらん」と言って呉れた。
う〜ん。かもね〜とは思ったが。
そして二巻は買わないと言っている。
う〜ん。どうしよう〜。
森 薫 著 エンタープレイン刊
ようやく最終巻、というかもう最終巻?
著者のあとがきを読むと、真面目に感想&希望のハガキに沿ってエピソードを書いていたらしいので、「あーじゃあ書けばよかったかぁ」と思った。
もちろん作者の希望(リスの話とか、歌手の話とか)も優先されたようだが、希望は叶ったかもしれない。ちょっと残念。
番外編最終巻は、そりゃあもう結婚式でしょう。
この表紙のお二人の。
それなりに時間を要したようです。
ラヴラヴです。
ハキム(インド人の彼)もやはり素敵です。
…というわけで、これ以上のネタばれは語らないが花♪
ああ、感動的なのは結婚式だけど、一番おもしろかったのは四コマ漫画かも?
ようやく最終巻、というかもう最終巻?
著者のあとがきを読むと、真面目に感想&希望のハガキに沿ってエピソードを書いていたらしいので、「あーじゃあ書けばよかったかぁ」と思った。
もちろん作者の希望(リスの話とか、歌手の話とか)も優先されたようだが、希望は叶ったかもしれない。ちょっと残念。
番外編最終巻は、そりゃあもう結婚式でしょう。
この表紙のお二人の。
それなりに時間を要したようです。
ラヴラヴです。
ハキム(インド人の彼)もやはり素敵です。
…というわけで、これ以上のネタばれは語らないが花♪
ああ、感動的なのは結婚式だけど、一番おもしろかったのは四コマ漫画かも?
コーセルテルの竜術士物語(6)
2008年5月2日 読書
石動あゆま 著 一迅社刊
竜の子、子育てほのぼのファンタジーである。
ほんま、ほのぼのする〜物語は単純だが、なんか惹かれる。
最初から登場人物の全部の情報を明かさず、物語の進展に従って徐々に明らかになってゆく、というのは普通の物語の進展である。
だが、主役の秘密(?)をここまでたくさん持たせる物語もすごい。
いや、秘密でも何でもないことを、基本設定としてきちんと読者に語らない物語も凄い。
6巻にもなって、家族関係がぽろりと出てきた始末。
なんじゃい、それは(今頃)
それで面白く読んでいる読者も凄い(笑)
設定とか人間関係とか、そういうものの外に魅力がある証拠か。
竜の子、子育てほのぼのファンタジーである。
ほんま、ほのぼのする〜物語は単純だが、なんか惹かれる。
最初から登場人物の全部の情報を明かさず、物語の進展に従って徐々に明らかになってゆく、というのは普通の物語の進展である。
だが、主役の秘密(?)をここまでたくさん持たせる物語もすごい。
いや、秘密でも何でもないことを、基本設定としてきちんと読者に語らない物語も凄い。
6巻にもなって、家族関係がぽろりと出てきた始末。
なんじゃい、それは(今頃)
それで面白く読んでいる読者も凄い(笑)
設定とか人間関係とか、そういうものの外に魅力がある証拠か。
デセプション・ポイント(下)
2008年5月2日 読書
内視鏡での処置日だったが、下巻に手を出してしまった……
だって飲食できないし。
退屈だし。
まあそれぐらいに引き込まれる本であったということだ。
情報分析のスペシャリストにして、現職大統領に喧嘩を売っている上院議員の娘でもあるレイチェルである。
30代半ば…のはずだが、一緒に命を狙われている海洋学者と宇宙学者と、三人ですごいアクションのすえ、なんとかかんとか危機一髪で逃げまくっているのがすごい。
彼らの口をふさごうとする本人は、自分が正義だと思っているが、その?氏が登場するのが最後の最後。
(これだと部下がかわいそうだよぅ)
……
だまされたー!(笑)
うまいよーダン・ブラウン!
ってところでしょうか。
「大義のための小さな犠牲」とは、加害者が言うセリフだ。
自分が被害者で言うならまだわかるが、ミサイルで狙いをつけられて言われても、納得できるセリフではないよなぁ。
ある女性の心の揺れ動き方が、とっても微妙で良くわかる。
どっちにつくの?とは思ったし、でも最後は泣いて逃げてゆくのかなと思ったら、ものすごいメガトン級のしっぺ返しをしてしまった…さすがアメリカ女性だ。
ラストがハッピー♪なのは、作者が人間というものを最終的には信じている証拠ではないだろうか。
何かの形で希望を抱きたい、というメッセージではないかと思う。
ところで、読後の感想のひとつとしては、ハンマーシャークがあったかい海が好き♪という雑学は不要だった気がする…
だって飲食できないし。
退屈だし。
まあそれぐらいに引き込まれる本であったということだ。
情報分析のスペシャリストにして、現職大統領に喧嘩を売っている上院議員の娘でもあるレイチェルである。
30代半ば…のはずだが、一緒に命を狙われている海洋学者と宇宙学者と、三人ですごいアクションのすえ、なんとかかんとか危機一髪で逃げまくっているのがすごい。
彼らの口をふさごうとする本人は、自分が正義だと思っているが、その?氏が登場するのが最後の最後。
(これだと部下がかわいそうだよぅ)
……
だまされたー!(笑)
うまいよーダン・ブラウン!
ってところでしょうか。
「大義のための小さな犠牲」とは、加害者が言うセリフだ。
自分が被害者で言うならまだわかるが、ミサイルで狙いをつけられて言われても、納得できるセリフではないよなぁ。
ある女性の心の揺れ動き方が、とっても微妙で良くわかる。
どっちにつくの?とは思ったし、でも最後は泣いて逃げてゆくのかなと思ったら、ものすごいメガトン級のしっぺ返しをしてしまった…さすがアメリカ女性だ。
ラストがハッピー♪なのは、作者が人間というものを最終的には信じている証拠ではないだろうか。
何かの形で希望を抱きたい、というメッセージではないかと思う。
ところで、読後の感想のひとつとしては、ハンマーシャークがあったかい海が好き♪という雑学は不要だった気がする…