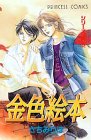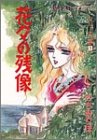天使達は闇夜に囁く 1 (1)
2007年6月15日 読書
時は19世紀(?ごろ?)
場所はオーストリーの首都・ウイーン……最初は思い込みで倫敦だとばかり。
だって川とか橋とか出てくれば、てっきり倫敦ブリッジかと思うじゃないか。
まあいいや。
贅沢三昧なに不自由なく暮らす貴族さまは、何を考つくやらさっぱりわからん。
不老不死を臨むお貴族さまは、それが唯一自由にならないものだからだそうだ。
その日暮の貧しいヒロイン・チェルシーにはわからない考えである。
そのチェルシーが出会ったこの二人。
金髪のエルネストと黒髪のアレクシス。彼らにはなにかとんでもない秘密があるらしい……。
あまりその正体を考えたくない二人、エル&アル。
否が応でもその二人とのかかわりを深めてゆくチェル。
彼らはこの歪んだ社会の中で、どこへ行こうというのか?
…ということで、今のところはまだ様子見の段階である。
まあ、まえの「ヴァルキュリア」が強烈だったからなー(笑)
あれに対抗しようというのは、如何にも(蛸にも)しんどい。
ISBN:4253194818 コミック さちみ りほ 秋田書店 2007/04/16 ¥410
場所はオーストリーの首都・ウイーン……最初は思い込みで倫敦だとばかり。
だって川とか橋とか出てくれば、てっきり倫敦ブリッジかと思うじゃないか。
まあいいや。
贅沢三昧なに不自由なく暮らす貴族さまは、何を考つくやらさっぱりわからん。
不老不死を臨むお貴族さまは、それが唯一自由にならないものだからだそうだ。
その日暮の貧しいヒロイン・チェルシーにはわからない考えである。
そのチェルシーが出会ったこの二人。
金髪のエルネストと黒髪のアレクシス。彼らにはなにかとんでもない秘密があるらしい……。
あまりその正体を考えたくない二人、エル&アル。
否が応でもその二人とのかかわりを深めてゆくチェル。
彼らはこの歪んだ社会の中で、どこへ行こうというのか?
…ということで、今のところはまだ様子見の段階である。
まあ、まえの「ヴァルキュリア」が強烈だったからなー(笑)
あれに対抗しようというのは、如何にも(蛸にも)しんどい。
ISBN:4253194818 コミック さちみ りほ 秋田書店 2007/04/16 ¥410
ひゃっほう♪
これも友人からのレンタル本。
相変わらずの重さと太さでもちにくいが、大好きなストーリーなので、思わず会社にまでもって言って昼休みに読みふけっている……。
それでもまだまだ半分いってないなぁ。
所謂、古本屋主人・京極本、は屁理屈…じゃない、理屈が多くて読んでいて辛い時もあるのだが、こっちはそうでもない。
江戸時代の怪異を、堂読み解くか。
人の意識でなんとでも変わる現象を、読み解くのも一興、そのまま心霊の奥深くに沈めておくのもまた一興。
巷説というぐらいだから、巷(=世間)であれやこれや勝手なことを言い合う噂話…の物語。
百介さんはそーゆー物語を集めている人間だからして、そういう題名にもなるのだろうが、気分はほとんど「都市伝説」
現代史で言うところの、「口裂け女」とか。
そーゆーことらしい。
…で、
波長が合うのか?
好みがあうのか?
私はこっちのシリーズのほうが断然、好きなんである。
全作品の主役(多分)百介が、好々爺になってしまった明治の御世。
ほどほど文明開化された社会なのに、まだまだ怪異現象は残っている。
ああだこうだ、と仲間内で話がはずみ、はずんだ配意がまとまらないので、好事家のじいさまのところへ出かけていって意見を拝聴しようではないか、年の功は侮りがたし、目を開かされることもあろう、と百介のもとへ出かけてくる若者達。
西洋帰りの知識を総動員してみても、判らぬものはわからぬままだ…。
登場人物(もめる若者たち)の数が多いのが少々うッとおしいが(誰が誰だっけ…?)、話は良い。
面白い。
いいなぁ……。
この世界はいい。
なんか最後ははぐらかされる様な、理詰めで追求しきらないところ。
なんとなく〜こんな感じ?
で終わっちゃうところがいいのでは、と思う。
ISBN:4048735012 単行本 京極 夏彦 角川書店 2003/12 ¥2,100
これも友人からのレンタル本。
相変わらずの重さと太さでもちにくいが、大好きなストーリーなので、思わず会社にまでもって言って昼休みに読みふけっている……。
それでもまだまだ半分いってないなぁ。
所謂、古本屋主人・京極本、は屁理屈…じゃない、理屈が多くて読んでいて辛い時もあるのだが、こっちはそうでもない。
江戸時代の怪異を、堂読み解くか。
人の意識でなんとでも変わる現象を、読み解くのも一興、そのまま心霊の奥深くに沈めておくのもまた一興。
巷説というぐらいだから、巷(=世間)であれやこれや勝手なことを言い合う噂話…の物語。
百介さんはそーゆー物語を集めている人間だからして、そういう題名にもなるのだろうが、気分はほとんど「都市伝説」
現代史で言うところの、「口裂け女」とか。
そーゆーことらしい。
…で、
波長が合うのか?
好みがあうのか?
私はこっちのシリーズのほうが断然、好きなんである。
全作品の主役(多分)百介が、好々爺になってしまった明治の御世。
ほどほど文明開化された社会なのに、まだまだ怪異現象は残っている。
ああだこうだ、と仲間内で話がはずみ、はずんだ配意がまとまらないので、好事家のじいさまのところへ出かけていって意見を拝聴しようではないか、年の功は侮りがたし、目を開かされることもあろう、と百介のもとへ出かけてくる若者達。
西洋帰りの知識を総動員してみても、判らぬものはわからぬままだ…。
登場人物(もめる若者たち)の数が多いのが少々うッとおしいが(誰が誰だっけ…?)、話は良い。
面白い。
いいなぁ……。
この世界はいい。
なんか最後ははぐらかされる様な、理詰めで追求しきらないところ。
なんとなく〜こんな感じ?
で終わっちゃうところがいいのでは、と思う。
ISBN:4048735012 単行本 京極 夏彦 角川書店 2003/12 ¥2,100
自分が経験した"理不尽さ"や"哀しさ"や"生きる喜び"
なんてものを、この作者は無駄にしない。
感情移入してしまうのは、そういう作者の思いをまともに受け取ってしまうから…?
ま、見てて楽しいハンサムさんが登場するというのも大きな理由ではあるが……。
ISBN:4253077692 コミック さちみ りほ 秋田書店 2001/07 ¥410
なんてものを、この作者は無駄にしない。
感情移入してしまうのは、そういう作者の思いをまともに受け取ってしまうから…?
ま、見てて楽しいハンサムさんが登場するというのも大きな理由ではあるが……。
ISBN:4253077692 コミック さちみ りほ 秋田書店 2001/07 ¥410
ちょっとしんどくて、ぐだぐらしたい時には、やはりこういうのがいい。
優しさと。
哀しさと。
人間の限り在る資源である命を題材に、その思いを昇華させる。
単なる邪霊祓いではないんだよね。
おしらさま。
古代日本の信仰心と思念はすごいエネルギーだよね、と思う。
ISBN:4253077668 コミック さちみ りほ 秋田書店 1995/04 ¥410
優しさと。
哀しさと。
人間の限り在る資源である命を題材に、その思いを昇華させる。
単なる邪霊祓いではないんだよね。
おしらさま。
古代日本の信仰心と思念はすごいエネルギーだよね、と思う。
ISBN:4253077668 コミック さちみ りほ 秋田書店 1995/04 ¥410
図説中国の神々―道教神と仙人の大図鑑
2007年6月11日 読書道教と仙人の事典…みたいなもの。
曼荼羅ならぬ仙人図など、中国独特の考え方と世界観とがひと目で見られるのがとっても楽しい。図版はカラーだし(笑)
道士、いな、仙人に成りたい。
と少しだけ、学生の頃から思っている。
寿命とか、義理とか、人情とか、な〜んにも考えない。
それが仙人。
それって、感情のない化け物だけど。
で、化け物らしく寿命がないわけだけど。
だから、少しだけ。
感情がなければ、寿命があっても面白くない。
ヘンに力のある皇帝なぞは、そうして不老不死を求め、あたら丹(水銀など)を服用して命を縮めた。
阿呆である。
でも、下手に力があるとそれが無限に在るように思えるのか。
今までの皆は失敗したけれど、自分なら成功すると思ってしまうのか。
不老不死。
財産。
自由自在に出没する。
天空を往く。
人間の欲を叶えるのが仙人であり、道教の神様なのか。
それをすべて超越するのが仙人であり、道教の神さまなのか。
その辺がどうもはっきりしないところである。
不老不死なんて究極のよくだと思うけど、それを得るのは、「欲」どころか、感情をもっていることもダメなようだし。
対極の仏教が輪廻転生、病気をすること、老いること、死ぬことのほかに、生きることの苦しみまでも並べて見せるのに対し、なんと道教は仙人は"なにも考えない"かのように見えることか(笑)
不老不死で何ものにもココロを動かされずに生きてゆく(というより、ただ在るだけ)のなら、もしかしたら、自ら死を選ぼうとするかもなぁ……私は。
だって、面白くないもん。
常に笑いを撮りたい(?)関西人としては。
道教の神さまや仙人にはこんなに面白い(変な)のが揃っているのになぁ。
ISBN:4056047014 単行本 学習研究社 2007/03 ¥1,575
曼荼羅ならぬ仙人図など、中国独特の考え方と世界観とがひと目で見られるのがとっても楽しい。図版はカラーだし(笑)
道士、いな、仙人に成りたい。
と少しだけ、学生の頃から思っている。
寿命とか、義理とか、人情とか、な〜んにも考えない。
それが仙人。
それって、感情のない化け物だけど。
で、化け物らしく寿命がないわけだけど。
だから、少しだけ。
感情がなければ、寿命があっても面白くない。
ヘンに力のある皇帝なぞは、そうして不老不死を求め、あたら丹(水銀など)を服用して命を縮めた。
阿呆である。
でも、下手に力があるとそれが無限に在るように思えるのか。
今までの皆は失敗したけれど、自分なら成功すると思ってしまうのか。
不老不死。
財産。
自由自在に出没する。
天空を往く。
人間の欲を叶えるのが仙人であり、道教の神様なのか。
それをすべて超越するのが仙人であり、道教の神さまなのか。
その辺がどうもはっきりしないところである。
不老不死なんて究極のよくだと思うけど、それを得るのは、「欲」どころか、感情をもっていることもダメなようだし。
対極の仏教が輪廻転生、病気をすること、老いること、死ぬことのほかに、生きることの苦しみまでも並べて見せるのに対し、なんと道教は仙人は"なにも考えない"かのように見えることか(笑)
不老不死で何ものにもココロを動かされずに生きてゆく(というより、ただ在るだけ)のなら、もしかしたら、自ら死を選ぼうとするかもなぁ……私は。
だって、面白くないもん。
常に笑いを撮りたい(?)関西人としては。
道教の神さまや仙人にはこんなに面白い(変な)のが揃っているのになぁ。
ISBN:4056047014 単行本 学習研究社 2007/03 ¥1,575
いよいよ最終巻!
ヨーロッパから船で東南アジアを経由、そして日本へ…。
それもまた、妻・三千代とは別々に…嗚呼、この人ってばさ。
時代は戦争へ、まっしぐら、否、真ッさかさまに落ちてゆくところ。
帰りの東南アジアでは、排日感情丸出しの華僑その他の目の色におののきつつ、相変わらず茶目っ気(というか病気というか、あちこちに引っかかってばかりいるのが本当にすごいと思うよ)を忘れられない金子光晴氏であった。
さあ。彼は無事に日本にかえれるのか?(笑)
なんて、紙芝居のおじさんか講談師の科白のように言わなきゃならなくなりそうだ。
ISBN:4122004489 文庫 金子 光晴 中央公論新社 1977/06 ¥660
ヨーロッパから船で東南アジアを経由、そして日本へ…。
それもまた、妻・三千代とは別々に…嗚呼、この人ってばさ。
時代は戦争へ、まっしぐら、否、真ッさかさまに落ちてゆくところ。
帰りの東南アジアでは、排日感情丸出しの華僑その他の目の色におののきつつ、相変わらず茶目っ気(というか病気というか、あちこちに引っかかってばかりいるのが本当にすごいと思うよ)を忘れられない金子光晴氏であった。
さあ。彼は無事に日本にかえれるのか?(笑)
なんて、紙芝居のおじさんか講談師の科白のように言わなきゃならなくなりそうだ。
ISBN:4122004489 文庫 金子 光晴 中央公論新社 1977/06 ¥660
僕は、自分がそれほど頑丈でないことをしっているので東南アジアのジャングルの中、スコールにあって泥の川を漕ぐように前進しつつ……著者・金子光晴は言うのである。
うそばっかり……。
充分、強いです、貴方は。
今の日本人から見たら数倍、数十倍お強いですがな。
「どくろ杯」は、日本でのごたごた。
妻・森三千代との出会いと馴れ初め。
上海への旅立ち。
上海でのあれやこれや。
…で終了。
その続きは、この本で。
(なんか詐欺みたいやな……)
さて。
上海は、"とりあえず日本におられなくなった"やからが大挙して押し寄せる吹き溜まりのようなところであるので、ここで腐って腐臭を花って動けなくなる前に、著者夫婦は腰を上げた。
巴里に向かって出発しなければ、東京で待つ、妻・森三千代の若い恋人に彼女を渡す羽目になる。
ならば前に進むしかない。
それで、絵を書き同胞の情けに助けられつつシンガポールまでたどり着く。
途中の香港は物価ばかり高くて、良いことはなかった様子。
そこからは、妻一人を船に乗せ、先に巴里に行けと送り出し、自分はジャワやマレーやらを転々としながら金を稼いで後を追うつもり。
奥方は。
森三千代は、多分英語もそんなに出来ないんじゃないのか?
もしかして?
フランス語は出来ないと書いてある。
勉強しようにも、貧乏すぎて本も買えない生活だ。
もともと地方(地元)では首席を通して、御茶ノ水に入学したほどの才媛である。(そしてかなりの変人:昔はこーゆー感じだったのか、才媛ってのは。)
賢いのは賢い…でも、さぞかし心細かろうに、夫・金子光晴を信じたのか?
ちゃんと追いかけてきてくれると思っていたんだろうか?
それとも、どうせちゃらんぽらんだ、行ったら行ったで自分でなんとか生きてゆこう、ぐらいの気概があったのか。
なんでもあり、な感じがする…。
割れ鍋にとじぶた。
上手く出来てる、世の中は。
この文体。
この文章のイメージと言うか、感じる妖しさと言うか、…なにかを思い出す。
なんだろう、とおもったら、さっき気がついた。
江戸川乱歩だ。
江戸川乱歩のなんともいえない奇怪な匂いが漂っているのだ。
現代の漫画で言うなら高橋葉介か。
嵌まったら怖い…という、この本の貸主(友人)の科白に頷く。
ISBN:412204541X 文庫 金子 光晴 中央公論新社 2005/06 ¥840
南京路に花吹雪 [少女向け:コミックセット]
2007年6月6日 読書 コメント (2)懐かしい、という本だから、やっぱり画像が……出ない、か。
これも好きな漫画だった。
主役は黄子満…同人のパロディで「キッコーマン!」なんてのもあったな(笑)
昭和の初期から戦争にかけて、大陸に、特に舞台は上海だったが、中国に渡ったもののそこで夢破れて阿片と酒に身を持ち崩して、ぐずぐずと…。
まさしくぐずぐずと腐って命を落としていった日本人達。
それは漫画で、さほどショックを感じはしなかったが、文章だけでここまでショックを感じるとは…。
いや、ショックではないか。
驚きと言うか、あの漫画のまま、というか。
この本の題名の、
「どくろ杯」
は象徴ではなく、まさしく人間の、しかも処女のどくろで作った酒盃であるとのこと。
そんなものを荷物から取り出して、「これを元手に勘を儲けて…」なんて朽ちたアパートの一室で打ち明けられてもねぇ。
しかも、例えばそんなこんな曰くの在る小金を手にした彼らが何をするかといえば、放蕩三昧。
近場の蘇州あたりにくりだして、贅沢に浪費する。
なんか、ぜんぜん建設的ではないんですけど。
こういう日本人がごろごろしていたようです。
それだけで、なんというか、何もいえないというか。
独特の世界だ。
一番近いのは、
20数年前の中国奥地(いろんな意味で)。
電気もまともにないのか、夜の夜中の露店で、灯りは豆電球ひとつ。
しかもその電線はどこから伸びているのやら判らない。
その電線の伸びる先は暗闇だから。
そのわずかな黄色いといか赤いというか…の灯の下に男たちが3〜4人集まってなにやらぼそぼそと喋っている。
そういう塊(島)が、ぽつん、ぽつん、と数箇所にある。
これが夜の市、だというのだから。
……なんというか、不気味な雰囲気の、宜昌の町。
あの光景が、目に焼きついている。
今ではぎんぎんぎらぎらの中国であるけれど、一歩路地に入ったら、判ったものではないぞ、と思う。
ISBN:B0000BX76L コミック 森川 久美 角川書店
これも好きな漫画だった。
主役は黄子満…同人のパロディで「キッコーマン!」なんてのもあったな(笑)
昭和の初期から戦争にかけて、大陸に、特に舞台は上海だったが、中国に渡ったもののそこで夢破れて阿片と酒に身を持ち崩して、ぐずぐずと…。
まさしくぐずぐずと腐って命を落としていった日本人達。
それは漫画で、さほどショックを感じはしなかったが、文章だけでここまでショックを感じるとは…。
いや、ショックではないか。
驚きと言うか、あの漫画のまま、というか。
この本の題名の、
「どくろ杯」
は象徴ではなく、まさしく人間の、しかも処女のどくろで作った酒盃であるとのこと。
そんなものを荷物から取り出して、「これを元手に勘を儲けて…」なんて朽ちたアパートの一室で打ち明けられてもねぇ。
しかも、例えばそんなこんな曰くの在る小金を手にした彼らが何をするかといえば、放蕩三昧。
近場の蘇州あたりにくりだして、贅沢に浪費する。
なんか、ぜんぜん建設的ではないんですけど。
こういう日本人がごろごろしていたようです。
それだけで、なんというか、何もいえないというか。
独特の世界だ。
一番近いのは、
20数年前の中国奥地(いろんな意味で)。
電気もまともにないのか、夜の夜中の露店で、灯りは豆電球ひとつ。
しかもその電線はどこから伸びているのやら判らない。
その電線の伸びる先は暗闇だから。
そのわずかな黄色いといか赤いというか…の灯の下に男たちが3〜4人集まってなにやらぼそぼそと喋っている。
そういう塊(島)が、ぽつん、ぽつん、と数箇所にある。
これが夜の市、だというのだから。
……なんというか、不気味な雰囲気の、宜昌の町。
あの光景が、目に焼きついている。
今ではぎんぎんぎらぎらの中国であるけれど、一歩路地に入ったら、判ったものではないぞ、と思う。
ISBN:B0000BX76L コミック 森川 久美 角川書店
大正末期。
著者夫妻は旅に出る。
金も当てもないというのに。
たいしたもんだ。
いけばどうにかなる、というのがあったみたい。
他の旅行集を読んでも、どこかへたどり着くと、その血の在留邦人をたずね、日本語で日本の話をする代わりにしばらく面倒を見てもらい、次の目的地の何某への紹介状などもちゃっかり貰って、次へと出発をしている。
その繰り返し。
ありがたきは、同郷、というか同国の友。
けっこー面倒を見てくれるもんだな、これが。
さほど海外雄飛する日本人がいなかったのと、数少ない日本人同士助け合おうという心がまだあったのか。
このご夫婦。
上海へ友人を案内し、ちょこっと出かけたのが運のつき。
またまた旅行熱が沸いて、幼い子供を妻の実家に預け夫婦で上海へ渡り、そのままジャワへ。
そしてあろうことか、ヨーロッパまで足を伸ばして7年間帰ってこなかった、というんだから、暢気と言うか無責任というか。
7年ですよ。6歳(小学校入学)の子供も13歳(中学生)になってますけど…。
ええんか、それで?
この時代、そんなんだったの?
いくらモボ・モガとかで自由を謳歌したとはいえ。
かたや、家族を引き連れ満州土を開墾せんと一大決心のもとに向かう。
かたや、しばし日本から姿を晦ます為に上海へ行く。
その違いを述べている。
大陸浪人…「夕日と拳銃」やな。
みっちり詰ったこの本を、読み上げるのはいつの日か(笑)
忘れた、忘れた、といいながら、これだけ書ければ立派なもんだ。
ISBN:4122044065 文庫 金子 光晴 中央公論新社 2004/08 ¥760
著者夫妻は旅に出る。
金も当てもないというのに。
たいしたもんだ。
いけばどうにかなる、というのがあったみたい。
他の旅行集を読んでも、どこかへたどり着くと、その血の在留邦人をたずね、日本語で日本の話をする代わりにしばらく面倒を見てもらい、次の目的地の何某への紹介状などもちゃっかり貰って、次へと出発をしている。
その繰り返し。
ありがたきは、同郷、というか同国の友。
けっこー面倒を見てくれるもんだな、これが。
さほど海外雄飛する日本人がいなかったのと、数少ない日本人同士助け合おうという心がまだあったのか。
このご夫婦。
上海へ友人を案内し、ちょこっと出かけたのが運のつき。
またまた旅行熱が沸いて、幼い子供を妻の実家に預け夫婦で上海へ渡り、そのままジャワへ。
そしてあろうことか、ヨーロッパまで足を伸ばして7年間帰ってこなかった、というんだから、暢気と言うか無責任というか。
7年ですよ。6歳(小学校入学)の子供も13歳(中学生)になってますけど…。
ええんか、それで?
この時代、そんなんだったの?
いくらモボ・モガとかで自由を謳歌したとはいえ。
満蒙へ出かけて行った浪人たちは、しきりに日本の捨石になることを広言したが、上海組は行ったり来たりをくり返して、用あり気な顔をしながら、何もせず半生を送る人間が多かった。とのこと。
かたや、家族を引き連れ満州土を開墾せんと一大決心のもとに向かう。
かたや、しばし日本から姿を晦ます為に上海へ行く。
その違いを述べている。
大陸浪人…「夕日と拳銃」やな。
みっちり詰ったこの本を、読み上げるのはいつの日か(笑)
忘れた、忘れた、といいながら、これだけ書ければ立派なもんだ。
ISBN:4122044065 文庫 金子 光晴 中央公論新社 2004/08 ¥760
ことば+α―狂言ことば京都ことば今日のことば
2007年6月2日 読書
狂言師である。
彼はDJなんかもしている人だ。
言葉を、とても大切にしているのだ。
なぜかといえば、狂言は「科白」で繋ぐ芸だから。
「〜ござる」で繋がれる言葉は、笑いを醸し出す。
中学校の時、授業の一環で狂言と歌舞伎を見に連れて行かれたが、面白い!とおもったのは狂言だった。(当たり前)
太郎冠者。
次郎冠者。
欲深い主。
主の大切な(秘蔵の)飴を舐め尽くした二人は、さあ、さて、どうするか……?
有名な「ぶす」の一幕。
ぶす、という語感が面白くてそれだけ覚えちゃったんである。
だから。
言葉は大切だよね。
狂言のことば。
京都のことば。
今日のことば。
この三つに分けて綴られている、エッセイ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
……つうわけで(笑)
笑いが止りません!
この本、MKタクシー会社の懸賞で当ったんです!うっふっふ♪
ちょっと気になっていた本が、MK新聞に懸賞で出ているなんて、な〜んてラッキー♪
とりあえず、欲しいものが見つかったらまずは懸賞を探そう!
そう思う私であった。
有難う!
MKさまっ!
ISBN:4838199503 単行本 茂山 千三郎 エフエム京都 2007/04 ¥1,575
彼はDJなんかもしている人だ。
言葉を、とても大切にしているのだ。
なぜかといえば、狂言は「科白」で繋ぐ芸だから。
「〜ござる」で繋がれる言葉は、笑いを醸し出す。
中学校の時、授業の一環で狂言と歌舞伎を見に連れて行かれたが、面白い!とおもったのは狂言だった。(当たり前)
太郎冠者。
次郎冠者。
欲深い主。
主の大切な(秘蔵の)飴を舐め尽くした二人は、さあ、さて、どうするか……?
有名な「ぶす」の一幕。
ぶす、という語感が面白くてそれだけ覚えちゃったんである。
だから。
言葉は大切だよね。
狂言のことば。
京都のことば。
今日のことば。
この三つに分けて綴られている、エッセイ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
……つうわけで(笑)
笑いが止りません!
この本、MKタクシー会社の懸賞で当ったんです!うっふっふ♪
ちょっと気になっていた本が、MK新聞に懸賞で出ているなんて、な〜んてラッキー♪
とりあえず、欲しいものが見つかったらまずは懸賞を探そう!
そう思う私であった。
有難う!
MKさまっ!
ISBN:4838199503 単行本 茂山 千三郎 エフエム京都 2007/04 ¥1,575
伯爵と愛人 2 (2)
2007年6月2日 読書
絵の違い、というか感触が違う…文月今日子の絵じゃないよ…とか思いつつ、最後のほうは結構楽しんで読んでいた。
フランス革命の初期においては、レンヌやブルターニュあたりはパリのぎしぎしした空気とは違う。
「俺たちはパリの政府に命令はされない。」
とか
「パリことはパリの人間が面倒を見る」
とか。
冷たい、というのではなくて、冷めている。
これが同じフランスという国のなかで、幾つもの地域・人種も分かれてしまっていることを如実に表わしているのか、と思う。
有名なバスクの独立運動だけではなく、只今現在ブルターニュもまた、フランスからの独立を目指している…(数年前の爆破事件など)
あのあたりは民族的にはケルトだからね。
アイルランドとかスコットランドとかとおんなじ。
イベントにはバグパイプ隊が花を添えたりする……。
マドレーヌは元伯爵のリュクと結婚式を挙げる。
だが素直に「愛している」といえない二人。
王党派の大物と目されるリュクは、次から次へとモンダイを(?)起こすし、素直じゃないから弁解もできないだしで、二人の関係は悪化を辿る。
ブルターニューの反革命派…ふくろう党、なんてあったのね…不勉強でした。
ISBN:4776715643 コミック 文月 今日子 宙出版 2005/03/01 ¥630
フランス革命の初期においては、レンヌやブルターニュあたりはパリのぎしぎしした空気とは違う。
「俺たちはパリの政府に命令はされない。」
とか
「パリことはパリの人間が面倒を見る」
とか。
冷たい、というのではなくて、冷めている。
これが同じフランスという国のなかで、幾つもの地域・人種も分かれてしまっていることを如実に表わしているのか、と思う。
有名なバスクの独立運動だけではなく、只今現在ブルターニュもまた、フランスからの独立を目指している…(数年前の爆破事件など)
あのあたりは民族的にはケルトだからね。
アイルランドとかスコットランドとかとおんなじ。
イベントにはバグパイプ隊が花を添えたりする……。
マドレーヌは元伯爵のリュクと結婚式を挙げる。
だが素直に「愛している」といえない二人。
王党派の大物と目されるリュクは、次から次へとモンダイを(?)起こすし、素直じゃないから弁解もできないだしで、二人の関係は悪化を辿る。
ブルターニューの反革命派…ふくろう党、なんてあったのね…不勉強でした。
ISBN:4776715643 コミック 文月 今日子 宙出版 2005/03/01 ¥630
伯爵と愛人 1 (1)
2007年6月1日 読書
ハーレークインな漫画、とあったので悩みに悩んだが。
フランス革命期の話、であるので思い切って買ってみた。
……絵柄が違いますよぅ(涙)
登場人物の動きが、表情がぎこちなく感じられるのは私だけ?
文月今日子氏に何があったの?!と聞きたくなってしまった……。
ISBN:4776715635 コミック 文月 今日子 宙出版 2005/03/01 ¥630
フランス革命期の話、であるので思い切って買ってみた。
……絵柄が違いますよぅ(涙)
登場人物の動きが、表情がぎこちなく感じられるのは私だけ?
文月今日子氏に何があったの?!と聞きたくなってしまった……。
ISBN:4776715635 コミック 文月 今日子 宙出版 2005/03/01 ¥630
金のアレクサンドラ (2)
2007年6月1日 読書
この大ドラマを二巻で収めるか……さすが。
エジプトへ到達。
しかし、アレクサンドラが恋するイナールの目的はもうひとつあった…つうか、最初にそういうことを言っていたのをすっかり忘れていたのだけど。
当時、海賊天国・地中海に面するヨーロッパの町・村。
そこに住む人々はとっても大変だった。
あたかも北の平原から馬を疾駆させやってくる騎馬民族みたいなものだ。
天高く馬肥ゆる秋……略奪者がやってくる。
バーバリー海賊のほうは季節はお構いなし。
それに対抗するために、頑丈な砦も作られた。
数日間そこにこもって持ちこたえれば、海賊は(そのときは)諦めて(その時は)引き上げる。
白人奴隷で市場は賑わい、ガレー船のこぎ手で一生を終える男たち。
ハレムに売られ自由のないまま一生を終える女達。
その辺り、小説「アンジェリーク」にも詳しい。
そういう時代である。
ISBN:4834273407 文庫 文月 今日子 ホーム社 2005/07 ¥700
エジプトへ到達。
しかし、アレクサンドラが恋するイナールの目的はもうひとつあった…つうか、最初にそういうことを言っていたのをすっかり忘れていたのだけど。
当時、海賊天国・地中海に面するヨーロッパの町・村。
そこに住む人々はとっても大変だった。
あたかも北の平原から馬を疾駆させやってくる騎馬民族みたいなものだ。
天高く馬肥ゆる秋……略奪者がやってくる。
バーバリー海賊のほうは季節はお構いなし。
それに対抗するために、頑丈な砦も作られた。
数日間そこにこもって持ちこたえれば、海賊は(そのときは)諦めて(その時は)引き上げる。
白人奴隷で市場は賑わい、ガレー船のこぎ手で一生を終える男たち。
ハレムに売られ自由のないまま一生を終える女達。
その辺り、小説「アンジェリーク」にも詳しい。
そういう時代である。
ISBN:4834273407 文庫 文月 今日子 ホーム社 2005/07 ¥700
金のアレクサンドラ (1)
2007年6月1日 読書
豪華な絵を描く人だよね、本当に。
すごい。
ガレー船だけど、いい!
美しい!
海と帆船(手漕ぎ付きのガレー船だけど)があればそれでもいいや。
バルバロッサも出てくるけど、まあいいや。
ハンサムな海賊とかハンサムなマムルークとかハンサムなベネチアの官僚とか元ハンサムなパパとか出てくるし。
不惑に届いても若い男に対抗して彼女の愛を勝ち取ろうとするハンサムガイもいることだし。
なんと色とりどり。
彩色に満ち溢れた物語だろう。
中世ヨーロッパ、その中でも異色のベネチアをてんこ盛り盛り込んだ歴史浪漫。
ベネチアの貴族の令嬢が母の故郷(エジプト)に恋焦がれ、家でして密航して海賊と恋をしてまで(?)たどり着いたエジプト。
彼女を待ち受ける運命はいかに!?
おてんばの一言では済まされない令嬢・アレクサンドラ。
彼女の未来に栄光あれ…!
一番、なにより素敵だったのは、これ。
斜陽のベネチア。
1492年のコロンブスの新大陸発見や、ガマのインド航路発見など、後発組の若手新興国に背中をたたかれるぐらいならまだしも、蹴り飛ばされ踏みつけられ、老人は後からおいで、あるいは、隠居せよと最終通知を突きつけられつつ、負けていない都市国家である。
末期症状を呈しつつ、なんの、まだまだ若いもんにはまけじ!とばかり、輿を折りつつ咳き込みつつ陰謀を企む老獪なベネチアが、如何にも!という感じでよかった。
大丈夫だとも。
ポルトガルもスペインもじき老いる。
同じように年寄りとして、若い新興国の勃興を見つめることになる日も存外に近いのだから。
ISBN:4834273377 文庫 文月 今日子 ホーム社 2005/06 ¥700
すごい。
ガレー船だけど、いい!
美しい!
海と帆船(手漕ぎ付きのガレー船だけど)があればそれでもいいや。
バルバロッサも出てくるけど、まあいいや。
ハンサムな海賊とかハンサムなマムルークとかハンサムなベネチアの官僚とか元ハンサムなパパとか出てくるし。
不惑に届いても若い男に対抗して彼女の愛を勝ち取ろうとするハンサムガイもいることだし。
なんと色とりどり。
彩色に満ち溢れた物語だろう。
中世ヨーロッパ、その中でも異色のベネチアをてんこ盛り盛り込んだ歴史浪漫。
ベネチアの貴族の令嬢が母の故郷(エジプト)に恋焦がれ、家でして密航して海賊と恋をしてまで(?)たどり着いたエジプト。
彼女を待ち受ける運命はいかに!?
おてんばの一言では済まされない令嬢・アレクサンドラ。
彼女の未来に栄光あれ…!
一番、なにより素敵だったのは、これ。
斜陽のベネチア。
1492年のコロンブスの新大陸発見や、ガマのインド航路発見など、後発組の若手新興国に背中をたたかれるぐらいならまだしも、蹴り飛ばされ踏みつけられ、老人は後からおいで、あるいは、隠居せよと最終通知を突きつけられつつ、負けていない都市国家である。
末期症状を呈しつつ、なんの、まだまだ若いもんにはまけじ!とばかり、輿を折りつつ咳き込みつつ陰謀を企む老獪なベネチアが、如何にも!という感じでよかった。
大丈夫だとも。
ポルトガルもスペインもじき老いる。
同じように年寄りとして、若い新興国の勃興を見つめることになる日も存外に近いのだから。
ISBN:4834273377 文庫 文月 今日子 ホーム社 2005/06 ¥700
Landreaall 10 (10)
2007年6月1日 読書
待ちに待った、第10巻…そしてまだまだ続きそうなのが嬉しい。
待ていたくせに、「本屋に届いてます」の知らせを聞きつつすっかり忘れている私だ(笑)
どこまでカッコいいんだ!リオンちゃん。
でも私はアンちゃんの味方。
高所恐怖症とは気が合うねぇ(笑)
猫使い…まさしく!
可愛いじゃないの。
巨大猫もね。
乗せて走ってくれるし。
そして素敵なおかーさま!
バズーカ砲みたいなの抱えて再びみたびの登場だ。
龍と闘って生き残った女傭兵……そう、勝った負けたではなく、龍と闘えば"生き残った"事こそが勲章なのだ。
ISBN:4758052875 コミック おがき ちか 一迅社 2007/05/25 ¥580
待ていたくせに、「本屋に届いてます」の知らせを聞きつつすっかり忘れている私だ(笑)
どこまでカッコいいんだ!リオンちゃん。
でも私はアンちゃんの味方。
高所恐怖症とは気が合うねぇ(笑)
猫使い…まさしく!
可愛いじゃないの。
巨大猫もね。
乗せて走ってくれるし。
そして素敵なおかーさま!
バズーカ砲みたいなの抱えて再びみたびの登場だ。
龍と闘って生き残った女傭兵……そう、勝った負けたではなく、龍と闘えば"生き残った"事こそが勲章なのだ。
ISBN:4758052875 コミック おがき ちか 一迅社 2007/05/25 ¥580
桜闇―建築探偵桜井京介の事件簿
2007年5月31日 読書
かの、建築家探偵、むっつり根暗の桜井さんのお出ましである。
桜の季節は過ぎたけど、今年も桜は堪能したし(去年ほどではないが)思い出しながら読むことにしよう……。
それにしても、「鬼」でも出てきそうな題名だね。
薪能ででもやりそうな……。
あれ?
10の謎ってことは…短編集なのかな?
それならわかる、という700ページ弱の厚さ!
ISBN:4062751879 文庫 篠田 真由美 講談社 2005/09 ¥940
桜の季節は過ぎたけど、今年も桜は堪能したし(去年ほどではないが)思い出しながら読むことにしよう……。
それにしても、「鬼」でも出てきそうな題名だね。
薪能ででもやりそうな……。
あれ?
10の謎ってことは…短編集なのかな?
それならわかる、という700ページ弱の厚さ!
ISBN:4062751879 文庫 篠田 真由美 講談社 2005/09 ¥940
河童が覗いたヨーロッパ
2007年5月29日 読書 コメント (2)
これまたレンタル〜♪
いやぁ、絵が良いですね。
私はエッチングが大好きなんですが、この人の絵はそれに近い。
細密で、でもかちこちの直線ではなくて、微妙に曲がっていて味がある!
(以下、後日)
こういう絵、好きだな。
あったか味があるし、却って現実感が在る。
ヨーロッパをびんぼーくさく回る旅だというけれど、読んで見ている方は、とっても面白い。
私も買おうかな?と思ってしまった一冊だ。
(現在パリを放浪中也)
こういう海外のホテル事情をエッセイなどに綴った本が私は好きだ。
その原点が、昔々、地方局で中途半端な時間に放送していたとある番組。
「欧州旅籠事情」だったか「欧州旅籠紀行」「通信」だったか…なんかそんな名前の番組だった。
内容はといえば、外国(特にヨーロッパ)の各地で、地元の若くてうつくしーレディにホテルに泊まってもらうのだ。
勿論、ビジネスホテルではない。
バックパッカーご用達のお宿もない。
ちゃぁんとルームサービスがある(笑)日本式に言うと観光ホテルである。
で、夫々のホテルのサービスに点数をつけて合計点でどのレベルかを判断しましょう♪
…と、言うんだけどね。
その採点基準の細かいこと細かいこと!
まずは、ドアマンの応対、フロントの応対。
宿帳にサインをするとき、部屋へ案内するボーイの出てくる時間とか案内の仕方エトセトラエトセトラ……。
それだけではない。
部屋に入ったら、窓の外の眺め、騒音、掃除の具合、部屋の大きさ、ベッドメーキングの具合、調度品の使いやすさからバスルームの備品等々…とにかく、これでもか、これでもか、と、微に入り細に入りチャックをしまくる。
お風呂の温度も勿論、ルームサービスで紅茶を頼めば、もってくるまでの時間、お湯の温度……も、すちゃっと取り出した温度計で計る(笑)
そしてなんだか知らないが、サービスシーンとして、件の美女の入浴シーンが…(笑)
ちょびっと流れて、あとは"お休み"
そして、にこやかにチェックアウトする。
さて、このホテルの合計点はいかに?
という番組であった。
ホテル自体が画一的な日本のホテルとはまったく違い、夫々の個性をしっかり打ち出しているし、その調度品や部屋を見るだけでも値打ちものだったと思う。
まあ、自分が逆立ちしたって出会えそうもないホテルばかりだったけど…(まずヨーロッパに行かねばならない)
それゆえに毎回楽しく見ていたのだった。
あーゆー面白みの在る"大人の"番組。
最近ありませんなー。
ISBN:4062730618 文庫 妹尾 河童 講談社 2001/01 ¥630
いやぁ、絵が良いですね。
私はエッチングが大好きなんですが、この人の絵はそれに近い。
細密で、でもかちこちの直線ではなくて、微妙に曲がっていて味がある!
(以下、後日)
こういう絵、好きだな。
あったか味があるし、却って現実感が在る。
ヨーロッパをびんぼーくさく回る旅だというけれど、読んで見ている方は、とっても面白い。
私も買おうかな?と思ってしまった一冊だ。
(現在パリを放浪中也)
こういう海外のホテル事情をエッセイなどに綴った本が私は好きだ。
その原点が、昔々、地方局で中途半端な時間に放送していたとある番組。
「欧州旅籠事情」だったか「欧州旅籠紀行」「通信」だったか…なんかそんな名前の番組だった。
内容はといえば、外国(特にヨーロッパ)の各地で、地元の若くてうつくしーレディにホテルに泊まってもらうのだ。
勿論、ビジネスホテルではない。
バックパッカーご用達のお宿もない。
ちゃぁんとルームサービスがある(笑)日本式に言うと観光ホテルである。
で、夫々のホテルのサービスに点数をつけて合計点でどのレベルかを判断しましょう♪
…と、言うんだけどね。
その採点基準の細かいこと細かいこと!
まずは、ドアマンの応対、フロントの応対。
宿帳にサインをするとき、部屋へ案内するボーイの出てくる時間とか案内の仕方エトセトラエトセトラ……。
それだけではない。
部屋に入ったら、窓の外の眺め、騒音、掃除の具合、部屋の大きさ、ベッドメーキングの具合、調度品の使いやすさからバスルームの備品等々…とにかく、これでもか、これでもか、と、微に入り細に入りチャックをしまくる。
お風呂の温度も勿論、ルームサービスで紅茶を頼めば、もってくるまでの時間、お湯の温度……も、すちゃっと取り出した温度計で計る(笑)
そしてなんだか知らないが、サービスシーンとして、件の美女の入浴シーンが…(笑)
ちょびっと流れて、あとは"お休み"
そして、にこやかにチェックアウトする。
さて、このホテルの合計点はいかに?
という番組であった。
ホテル自体が画一的な日本のホテルとはまったく違い、夫々の個性をしっかり打ち出しているし、その調度品や部屋を見るだけでも値打ちものだったと思う。
まあ、自分が逆立ちしたって出会えそうもないホテルばかりだったけど…(まずヨーロッパに行かねばならない)
それゆえに毎回楽しく見ていたのだった。
あーゆー面白みの在る"大人の"番組。
最近ありませんなー。
ISBN:4062730618 文庫 妹尾 河童 講談社 2001/01 ¥630
友人からレンタルしました〜♪
この人も着物派だったとは……多いね、やっぱり。
(以下、後日)
お高い着物。
苦しい(笑)着物。
でも、とっても魅かれるのが、着物。
この二重苦(もっとある?)をクリアして、どうやれば着物を楽しめるか!?
その点を中心に着物本を書く人が、最近は多いね。
要は工夫、だというけれど。
でもやはり、「どこまで我慢できるか」がポイントだと思う。
京都では祇園祭りの宵山などで、浴衣姿のじょーちゃんが多くなった。
一時に比べれば、本当に多い。
でも、着崩れ?
それともわざと?
と首を捻る着方が多いのは確かで、「許せる」「許せない」の範囲が人によってさまざまだから、そこで問題が起こる。
「そんな着方をするならきるな!」
という断然正統強硬派もいれば、
「どうでも〜いい。」
とほとんど無関心派まで。
見た目に汚くだらしなく見える(感じる)のは、やっぱりダメだと思う。
自分風に着こなすのと、だらしなく着るのはまったくの別物。
「これはこういう着方なのよ!」
をいくら主張してみても、気が抜け力が抜けているものは、判ってしまう。
気合がはいてないって事、ばれてしまうのだ。
なぜか。
ぱっと見て「あ、いいな♪」「可愛いな♪」と思えるものは、確かにある。
センスの問題か。
いいな、と思えるのが数が少ないのが現状ではあるが。
残念。
ISBN:4198621926 単行本 近藤 ようこ 徳間書店 2006/07 ¥1,260
この人も着物派だったとは……多いね、やっぱり。
(以下、後日)
お高い着物。
苦しい(笑)着物。
でも、とっても魅かれるのが、着物。
この二重苦(もっとある?)をクリアして、どうやれば着物を楽しめるか!?
その点を中心に着物本を書く人が、最近は多いね。
要は工夫、だというけれど。
でもやはり、「どこまで我慢できるか」がポイントだと思う。
京都では祇園祭りの宵山などで、浴衣姿のじょーちゃんが多くなった。
一時に比べれば、本当に多い。
でも、着崩れ?
それともわざと?
と首を捻る着方が多いのは確かで、「許せる」「許せない」の範囲が人によってさまざまだから、そこで問題が起こる。
「そんな着方をするならきるな!」
という断然正統強硬派もいれば、
「どうでも〜いい。」
とほとんど無関心派まで。
見た目に汚くだらしなく見える(感じる)のは、やっぱりダメだと思う。
自分風に着こなすのと、だらしなく着るのはまったくの別物。
「これはこういう着方なのよ!」
をいくら主張してみても、気が抜け力が抜けているものは、判ってしまう。
気合がはいてないって事、ばれてしまうのだ。
なぜか。
ぱっと見て「あ、いいな♪」「可愛いな♪」と思えるものは、確かにある。
センスの問題か。
いいな、と思えるのが数が少ないのが現状ではあるが。
残念。
ISBN:4198621926 単行本 近藤 ようこ 徳間書店 2006/07 ¥1,260
復讐するは我にあり 改訂新版
2007年5月27日 読書
再刊本、ということで、宣伝に飛びついてしまったのだった。
この題名、この本の存在を知ったのは随分昔のことだが、縁のないままに過ごしてきた。
ただ、なんというか、怖い題名だよな、とは思っていた。
復讐譚?
あだ討ちするとか?
そういう話かと思っていたのだが。
最初に出てきたのは、そんな考えを一蹴するものだった。
聖書の言葉だったのだ。
では、イメージは180度変更される。
人は人に危害を当てるようなことはしてはならない。
たとえ自分が何をされたとしても。
目には目を、歯に歯を。
のハムラビ法典とは真逆の教えである。
では?
やっぱりなにか復讐されるようなことが起こったって事ですね……とは想像されるんだけどね。
昔の事件・事故の記録。
こんなことがありました。
という番組で、みたことがある。
日本列島を南から北まで(九州から北海道まで)、強盗殺人・詐欺・窃盗と罪に罪を重ねて逃げ回り、最後は幼い少女の勘によって逮捕された犯罪者の話。
その犯罪者・榎津巌を扱った小説なのであった。
榎津が、カトリック教徒(どこまで"本気の"信者なのかよくわからないが)であったこと、巌と言う名が洗礼名の"シモン"から付けられていること(シモンという人は、イエスに"わが岩(ペテロス)"と言われたらしい。だからその上に教会を建てるのだと。)など、読んでいくうち、彼のことが明らかになっているうちに、何故彼がそんなことを?といういろんな事がわかってくる……ンだろうなぁ、きっと。
今のところは彼の犯罪の、その後を追いかけるので精一杯、ひーひー言いながら後を追っている警察機構の話だけだ。
偽装自殺を早々に見破ったり、関係者をなだめすかしてうまく証言を引き出したりと、その辺の"技"は流石であるが。
小説としては、実に面白い。
重い本だが、出かけるときにも是非もって出たい、と思わせる本である。
ISBN:4902116804 単行本 佐木 隆三 弦書房 2007/03 ¥2,520
この題名、この本の存在を知ったのは随分昔のことだが、縁のないままに過ごしてきた。
ただ、なんというか、怖い題名だよな、とは思っていた。
復讐譚?
あだ討ちするとか?
そういう話かと思っていたのだが。
最初に出てきたのは、そんな考えを一蹴するものだった。
「愛する者よ、自ら復讐するな、ただ神の怒に任せまつれ。録して『主いい給う。復讐するは我にあり、我これを報いん』とあり」ロマ書12.19
聖書の言葉だったのだ。
では、イメージは180度変更される。
人は人に危害を当てるようなことはしてはならない。
たとえ自分が何をされたとしても。
目には目を、歯に歯を。
のハムラビ法典とは真逆の教えである。
では?
やっぱりなにか復讐されるようなことが起こったって事ですね……とは想像されるんだけどね。
昔の事件・事故の記録。
こんなことがありました。
という番組で、みたことがある。
日本列島を南から北まで(九州から北海道まで)、強盗殺人・詐欺・窃盗と罪に罪を重ねて逃げ回り、最後は幼い少女の勘によって逮捕された犯罪者の話。
その犯罪者・榎津巌を扱った小説なのであった。
榎津が、カトリック教徒(どこまで"本気の"信者なのかよくわからないが)であったこと、巌と言う名が洗礼名の"シモン"から付けられていること(シモンという人は、イエスに"わが岩(ペテロス)"と言われたらしい。だからその上に教会を建てるのだと。)など、読んでいくうち、彼のことが明らかになっているうちに、何故彼がそんなことを?といういろんな事がわかってくる……ンだろうなぁ、きっと。
今のところは彼の犯罪の、その後を追いかけるので精一杯、ひーひー言いながら後を追っている警察機構の話だけだ。
偽装自殺を早々に見破ったり、関係者をなだめすかしてうまく証言を引き出したりと、その辺の"技"は流石であるが。
小説としては、実に面白い。
重い本だが、出かけるときにも是非もって出たい、と思わせる本である。
ISBN:4902116804 単行本 佐木 隆三 弦書房 2007/03 ¥2,520
万葉明日香路―上山好庸写真集
2007年5月27日 読書
本日(5/26)はキトラ古墳の『玄武』公開に出かけてきた。
その土産に、こんなものを買ってきた。
「地元(飛鳥)出身の、有名な写真家さんなんですよ!」
とお店のおばちゃんに言われたものの…ごめん!
知らんのよ〜私。
だって、地元出身の○▲、というのは、地元の人だから知っている名前だったりすることが多い。
まあいい。
それは兎も角、中身をぱらぱらと見て、綺麗だったので買ってみた。
「綺麗よぅ」
(確かに)
「また(飛鳥に)来る時に、いいよぅ」
(いや、そんなしょっちゅうこんな遠方に来られへんし)
京都からだとたっぷり2時間はかかる。特急を使わなければ。
おばちゃんとのやり取りは以上。
まあ千円(税抜き価格で売ってくれた)だし。
そんなにおっきな写真集でもないし。
……綺麗だし。
ナニが綺麗って、飛鳥といえば田舎だ。(ごめん)
春や秋に、リュックを背負ってスニーカーで一日中歩いて気持ちよいような場所だ。
花は咲くし、田畑は広がっているし、鶯は鳴いている。
その、一番綺麗なところを、地元の強みで綺麗に切り取っている。
そういう写真だ。
石舞台の桜、もよいけど、紅花とか。
春のレンゲの群れ(田圃の中)とか。
あぜ道に咲く彼岸花、とか。
雪に埋もれる冬はゴメンだが…。
ああ、こんなところがあるんだなァとしみじみ思ったりする。
いい写真♪やっぱりしょっちゅうは来れないけど。
ISBN:4838102917 単行本 上山 好庸 光村推古書院 2001/10 ¥1,050
その土産に、こんなものを買ってきた。
「地元(飛鳥)出身の、有名な写真家さんなんですよ!」
とお店のおばちゃんに言われたものの…ごめん!
知らんのよ〜私。
だって、地元出身の○▲、というのは、地元の人だから知っている名前だったりすることが多い。
まあいい。
それは兎も角、中身をぱらぱらと見て、綺麗だったので買ってみた。
「綺麗よぅ」
(確かに)
「また(飛鳥に)来る時に、いいよぅ」
(いや、そんなしょっちゅうこんな遠方に来られへんし)
京都からだとたっぷり2時間はかかる。特急を使わなければ。
おばちゃんとのやり取りは以上。
まあ千円(税抜き価格で売ってくれた)だし。
そんなにおっきな写真集でもないし。
……綺麗だし。
ナニが綺麗って、飛鳥といえば田舎だ。(ごめん)
春や秋に、リュックを背負ってスニーカーで一日中歩いて気持ちよいような場所だ。
花は咲くし、田畑は広がっているし、鶯は鳴いている。
その、一番綺麗なところを、地元の強みで綺麗に切り取っている。
そういう写真だ。
石舞台の桜、もよいけど、紅花とか。
春のレンゲの群れ(田圃の中)とか。
あぜ道に咲く彼岸花、とか。
雪に埋もれる冬はゴメンだが…。
ああ、こんなところがあるんだなァとしみじみ思ったりする。
いい写真♪やっぱりしょっちゅうは来れないけど。
ISBN:4838102917 単行本 上山 好庸 光村推古書院 2001/10 ¥1,050